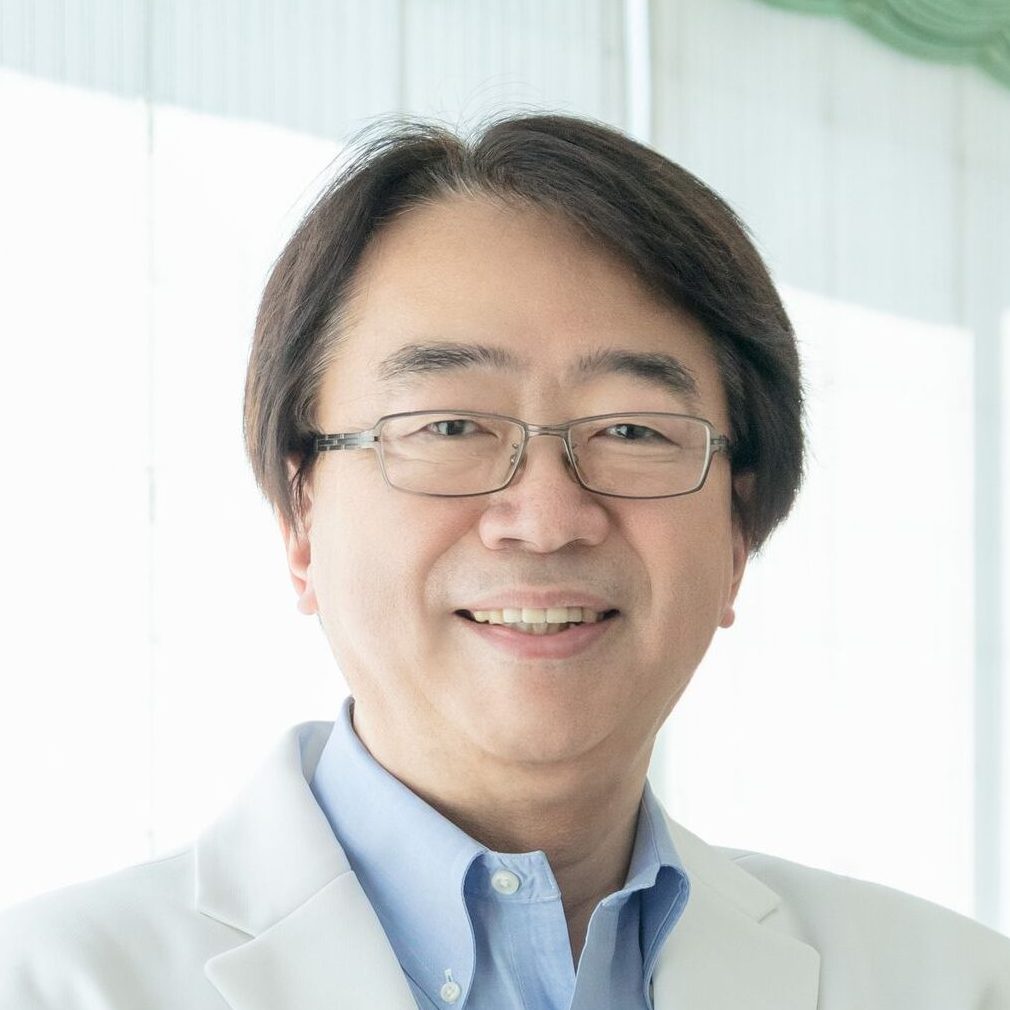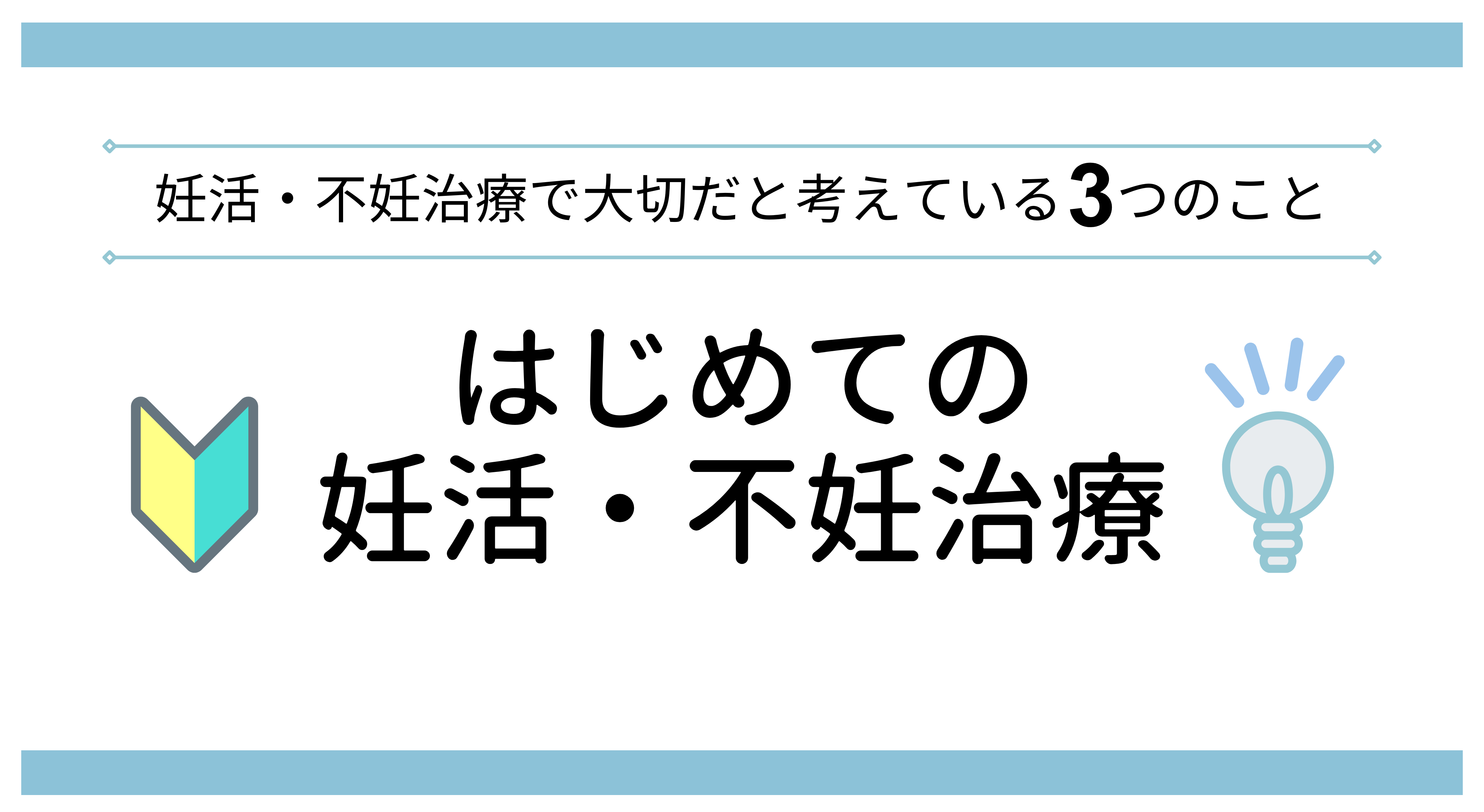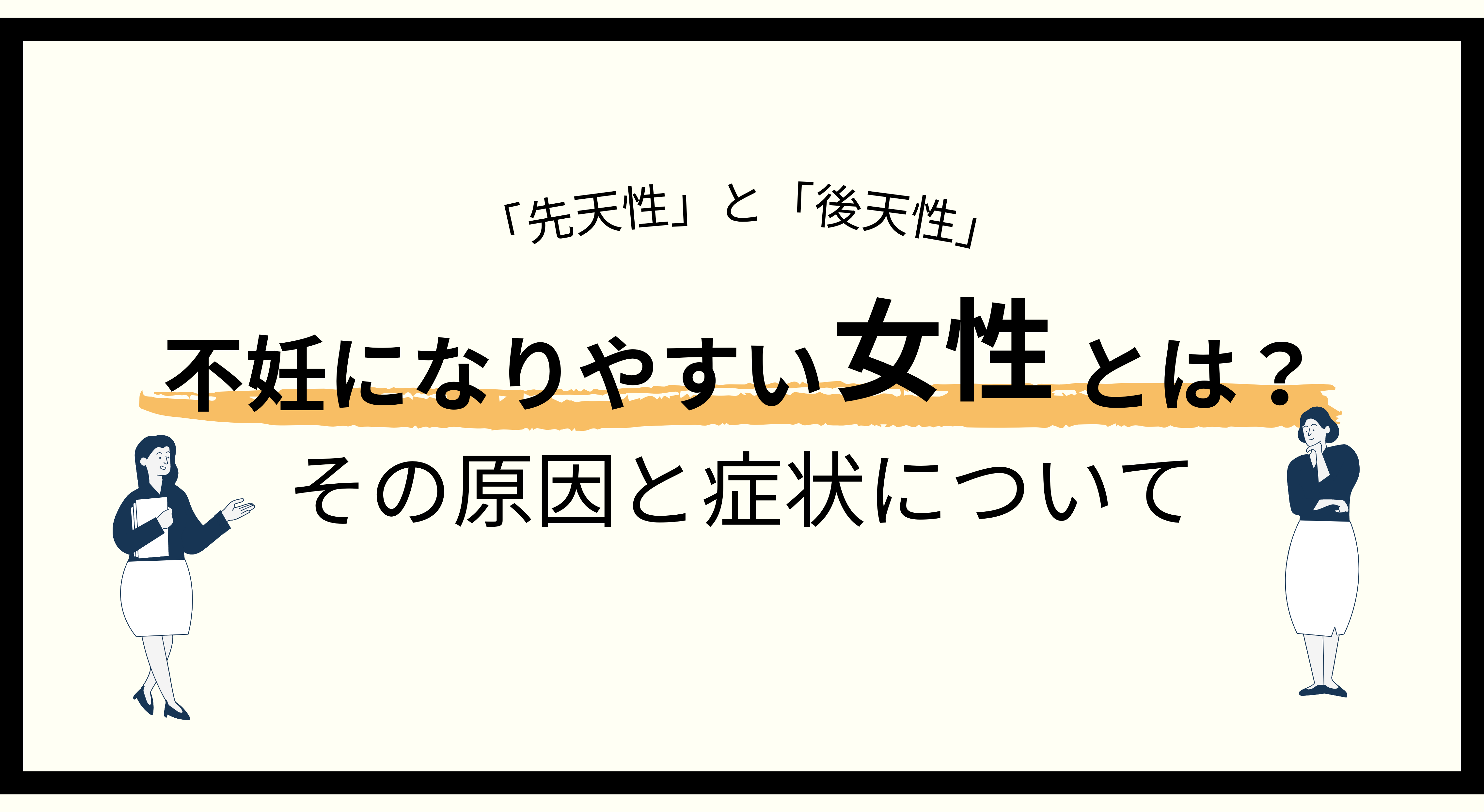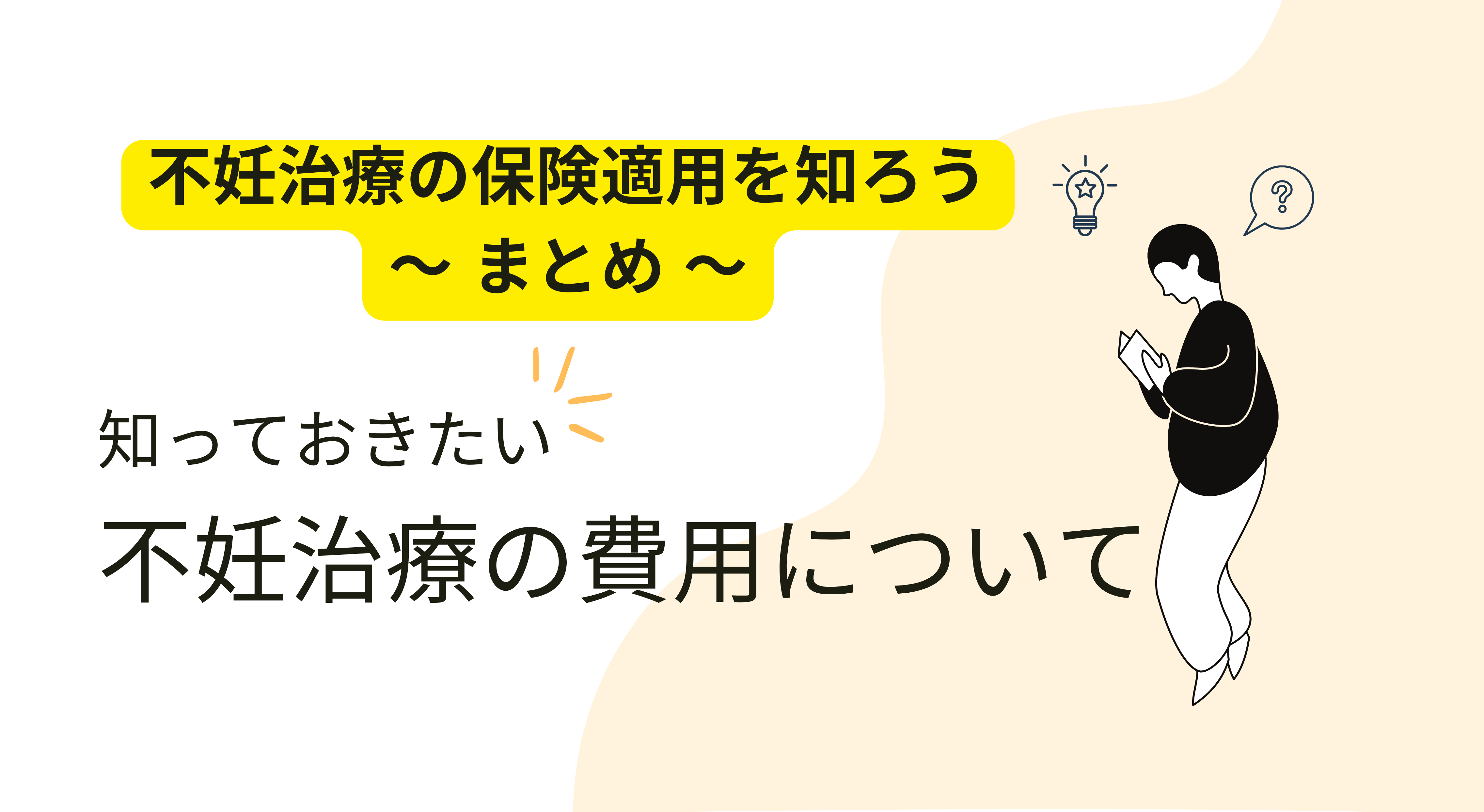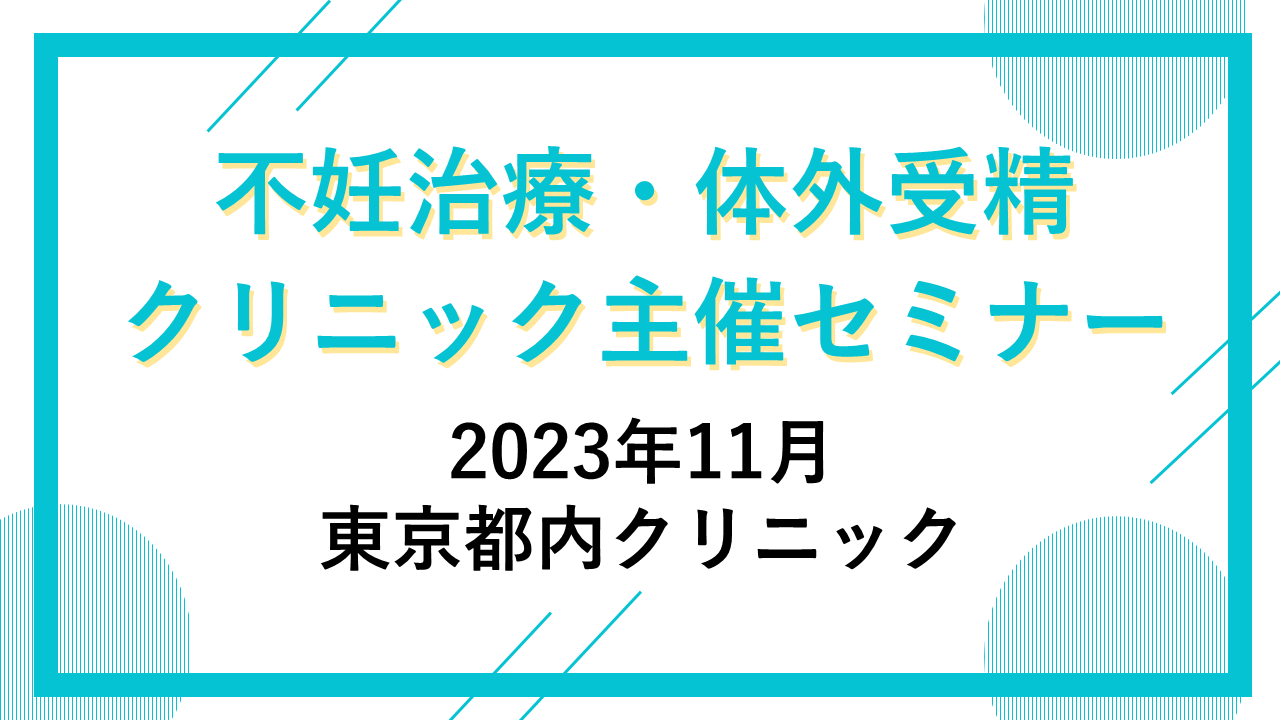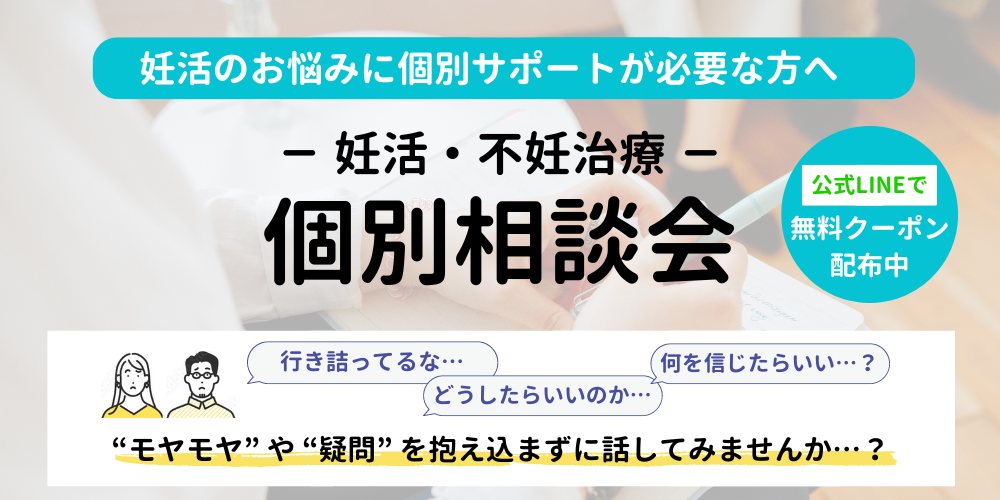まだ女性からだ情報局が立ち上がる前のこと。何人かの産婦人科医に「幅広く婦人科のことについて話を聞きたいのだが、都内で開業している方だとどなたが適任か」と尋ねたことがある。その際全員から挙がった名前が、広尾レディースの宗田聡(そうだ さとし)院長である。
かつてはその名の通り東京都港区広尾エリア*にあった「広尾レディース」は、お隣渋谷区の恵比寿駅前に移転しておよそ10年。広尾にあった頃から数えると18年以上にわたり、宗田医師は都内で婦人科医療に向き合ってきた。仮に年間300日・1日25名の診察を18年間続けたとすると、その延べ患者数は13万5,000人。渋谷区の女性人口がおよそ12万人だから、広尾レディースが積み上げてきた診察数は、渋谷区のすべての女性を超え、2周目に突入している。
(※編集部注:広尾駅前のエリアは渋谷区(広尾)と港区(南麻布)の境目のエリアにあり、かつての「広尾レディース」は港区に位置していた)
宗田医師が取り組むのは、クリニックでの診察だけではない。学会での発表や新しい事例の取り入れ、大学での学生たちへの教育、渋谷区の地域医療への関わり、そして“フェムテック”という言葉が世界で流行るずっと前から、女性のヘルスケア支援や啓発活動にも積極的だ。
体がいくつあっても足りないほどの活躍を見せる宗田医師だが、1日の終わりにクリニック周辺の写真をしばしばSNSへと投稿している。それを見て私たちは、今日も彼の多忙な1日が無事に終わったことを知るのだ。
「もうすぐ還暦だよ」と言いながら、その八面六臂の活躍は留まるところを知らない。だからこそ、昨年の女性からだ情報局の編集委員の立ち上げの際には、私たちに「宗田先生にお声かけをしない」という選択肢は無かった。就任をご快諾いただき、コンテンツの監修に精を出していただいたのは、読者の皆さんの知る通りだ。さらに昨年、忙しい日々の合間に宗田医師は「周産期マニュアル」というガッツリ書籍(774P!分厚い!)までをも刊行されている。
宗田医師のこの目覚ましい活躍を支えているものは何なのだろう。どのようにして誰もが名前を挙げるほど尊敬される存在に至ったのだろう。そこには「1000人に1人の重篤な疾患を見逃さないために」という、地域の婦人科クリニックならではの矜持がある。改めて宗田医師の抱える想いに迫った。

宗田医師が院長を務める広尾レディース
教師を目指す若者の人生を変えた、共通一次試験
宗田先生は、なぜ医師を目指されたんですか?
実は最初から医者を目指していた訳じゃなくて、もともとは小学校の教師になりたかったんです。親の影響で医者を目指すという人は多いですが、私の場合は父親はサラリーマンだし、親戚の中で医者だったのは母方の叔父さん。小さい頃は体が弱くて病院に行く機会が多くて、医者がかっこいいなぁと思ってはいたけれど、なりたいと思っていた訳ではなかった。
むしろずっと医者か獣医になりたいと言っていたのは弟の方だったんですよね。弟は生き物が大好きで、ファーブル昆虫記なんかを愛読する少年でした。一方私は生き物が苦手で、昆虫はもちろんダメだし、魚も苦手だから釣りもできない。魚は刺身とか切り身ならいいんですけど、顔が付いてる焼き魚だともう目が怖くて…。医者には珍しいかもしれません。
でも、医師になるには医学部に進学する必要がありますよね。大学受験までに目指すものが教師から医師に変わったんでしょうか?
高校になっても教師になる夢は変わっていなかったから、国公立の大学受験は茨城大学の教育学部が第一志望でした。私立は早稲田の教育学部と、サザンオールスターズのファンだったので桑田佳祐さんご出身の青山学院理工学部物理学科を受けようと(笑)。
いざ受験となって共通一次試験を受けてみたら、その点数が予想より少し良かった。
それで「もう少し偏差値の高いところを受験できるぞ」ってことで、筑波大学の医学部を受けることにしたんです。国公立であれば医学部に進んでも学費は変わらないし、サラリーマン家庭だったので浪人もさせないぞと言われていたし、受験は1回きりだったから思い切ってチャレンジしてみようって。
まぁ、サザンが好きで青学を受けようとしていたくらいだから、初めての大学受験を甘く考えていて、共通一次の結果が良かっただけで教育学部が医学部になってしまう(笑)。確かに親戚に医者はほとんどいなかったけど、唯一の医者だった叔父にはよく遊んでもらって身近な存在だったし、格好良いよなぁと。
当時の筑波大学医学部の受験内容は変わっていて、他大学に先駆けて2次試験では数学や英語などの科目が一切なくて、論文と集団面接のみだったんです。それもあって、2次対策を事前にしていなくても受験することができました。だから「どの時点で教師から医師に志望が変わったのか」という質問に答えるなら、「まさに受験の最中に」というのが答えですね。
それだけ生き物が苦手だと、受かったとは言え医学部進学に不安はありませんでしたか?
めちゃくちゃ迷いがありましたよ。医学部は医者になるための学部だから、やっていけるかどうかとても不安でした。特に当時の筑波大学医学部は、大学1〜2年の教養課程の時から医学の授業もあって、いきなり1年生から解剖の実習があったんです。だからある意味自分にとっての最初の試練で「入学早々に医者になれるかどうかがわかるな」と思っていました。ほら、生き物が苦手だったので。
ただ、逃げ道が無かった訳じゃなくて、中高生くらいの頃は科学小説やSFがとても好きだったので、「ジュラシック・パーク」や「ER緊急救命室」(TVシリーズの原作)を書いたマイケル・クライトンのように海外の作家や脚本家には医学部出身の人がいることも知っていた。だから、「医学部で医者になれなかったら物書きになろう」と思って割り切って入学したのを覚えています。
いざ人体を学んでみると、不思議なことに「人間の体ってなんてキレイなんだ」と思いました。他の生き物は全くダメなのに、植物でさえ苦手なのに、人の体は大丈夫だったんです。
振り返ってみると、私が本当の意味で心から医者を目指したのは、あの大学1年生の頃なのだと思います。
すべてが詰まった産婦人科で、すべてを身につけたかった日々
宗田先生が医療の中で「産婦人科」を選ばれたのはなぜですか?
今の医学部生は、色んな診療科を少しずつ経験した上で自分が進む診療科を選択できるみたいなんですが、私たちの時代は卒業までにどの科に進むかを選ばなくてはいけなかったんです。まだ実際に働いていないから「優秀な生徒は内科に」とか「外科は体育会系らしい」みたいに、噂と先輩の勧誘で選んでいくことがほとんどで。部活選びみたいですよね。
私は自分のことを優秀だとも体育会系だとも思っていなかったですし、1つの分野をとことん掘り下げていく診療科より、幅広く様々なことに関わっていきたいと思ったんです。産婦人科は内科的な治療も外科的な治療もあって、がんや分娩、ホルモン、スポーツ医学に至るまで、女性ならではの体のつくりや健康に関することすべてが詰まっている。そんなふうに産婦人科に惹かれ、その道に進むことにしました。

今でこそ「広尾レディース」で広く知られる宗田先生ですが、産婦人科を選んだ直後のキャリアはどのようなものだったんでしょうか。
医者には大学の「医局」という制度があるんですが、とにかく筑波大学の産婦人科の医局に所属している間は、臨床(編集部注:患者さんの治療)も研究も一生懸命やりましたね。
最初に5年間臨床現場で医師の仕事を学んだ後は、4年間大学院に通って遺伝子の研究をやりました。当時、お腹の赤ちゃんの病気の診断や治療を専門にしていて、そのために胎児の遺伝子に関する基礎研究を遺伝医学教室で一から学びました。
大学院で勉強したあとは、大学の講師として母校の学生と若手研修医の指導をしました。“教える”というのは臨床や研究とまた違った視点やスキルが必要だったので、新しいコミュニケーションも身につけることができ、学生さんや後輩医師とのやり取りも楽しかったです。その後、当時の文科省の在外研究員制度に申し込んだところ幸運にも選出されて、今もずっと仲良くさせていただいているビアンキ教授(現在はNIHの母子保健局の局長)のいるボストン(米国)に留学することもできました。
大病院では夜勤があったり、特に産婦人科は昼夜問わず分娩もあると思いますが、大変なことはありませんでしたか?
もちろん大変なことはたくさんありましたよ。大学病院の勤務医は夜勤どころか休日であっても、医師の体制によっては24時間いつでも呼び出される。プライベートなんてあったもんじゃない。もちろん今は医師もしっかりと休み、過剰労働はもちろんだめですし、それが本来の働く姿だとは思います。
そんな働きかたをしても、開業した同級生なんかと比べて金銭面の豊かさはレベルが違う。確かに20-30代の一般企業の同級生の平均所得より多いかもしれないけれど、24時間1週間休みなしの仕事なので時給換算するとめちゃくちゃ安かったんじゃないかと思います。
最近の医療界では比較的勤務時間が短くて給料のいい美容医療に進む医師が多いことも知っています。個人的には、そういった選択をする医師たちがいることも理解できます。でも、すべての医者が「高給・昼間のみ」っていう条件だけで診療科を選んでいたら、夜中に困っている患者さんを診てくれる医者がいない世の中になってしまう。今は医療従事者の労務管理が厳しくなったこともあり、本当に緊急を要する患者以外は後回しになってきています。「夜中に診てくれる医者がいない」は現実になりつつあるんです。
時代もあるけれど、あの頃文字通り身を粉にして働いていた私を支えてくれていたのは、やっぱり産婦人科医療が好きだったからなんです。自分がこの仕事にやりがいが見出せていたからこそ、一生懸命続けられてきた。
自分の治療で患者さんが治ってくれることも、幼い頃に自分がかっこいいと思っていた医師と同じように病気を治せていることも、知的な刺激が得られたり、色んな人と話すことができることもうれしかった。「人の喜ぶ顔をみたい」という思いの奥底には、教師になりたかった自分が今もいるのかもしれません。
“重篤な症状”の病院から、“病気の一歩手前”の世界へ
大病院から地域の婦人科へと活躍の場を移されたのには、どんな思いがあったのでしょうか。
医師免許を取得して、産婦人科に進んでからずっと大きな病院で産婦人科診療を続けてきたんですが、大病院だと診ている患者さんが「重篤な症状」であることが多いんです。ちょっとした体調不良だと、いきなり大病院には行かずに地域のクリニックを受診して、重篤な場合だけ紹介状を書いてもらって大病院に辿り着くという方がほとんどですからね。
産婦人科って“女性特有”だったり“女性に多い”病気を診ることが中心なんですが、大病院で主に重篤な症状の患者さんの診察を積み重ねていくと、「もっと早くに受診していれば…」とか「もっときちんと日々の健康管理をしておけば…」という患者さんもたくさんいて。
そういう人をもっと早く見つけたり、もっと早く受診してもらえるような医療をやっていきたいと思ったんです。大病院の『重篤な症状』の患者さんと比べるなら『病気の一歩手前』のところですよね。ここに取り組むには、「不安を感じたら、すぐに相談できるクリニック」がいいんじゃないかと思っていて、それは大病院では難しかった。それで40代半ばの頃に、地域の婦人科医療に身を投じることにしたんです。

宗田医師が患者と向き合う診察室
実際に大病院から地域の婦人科へと移られてみて、どんな変化を感じましたか?
さっきお話ししたように、役割が全く違うということですね。大病院に紹介されてくる患者さんは、そもそも何かの病気の疑いがある訳ですから、私が診ている時点で前の医師が疑った仮説がある。その仮説に沿って検査・診断して、治療を行うことが主な流れになります。
一方で地域のクリニックは「病気の一歩手前」ですから、患者さんが感じている不調の原因が何なのかを見極めなくてはいけない。重篤な病気を抱えた患者さんというのは割合としてはそう多くありませんが、999人が軽症であっても1人の重篤な病気の患者さんを絶対に見逃さない、そんなプレッシャーの中で診察を行うようになりました。「1,000人に1人の重篤疾患を見逃さないために、日々どれだけ腕を磨けるか」が治療をする上での主軸になったのが、大きな変化の1つです。
医者って医師免許を取ったら、そこから先は勉強しなくても失効することはないし、産婦人科専門医の資格を持っていなくても、医師免許さえあれば「婦人科/産婦人科」を自由に名乗ることができます。私は治療だけじゃなく新しい情報を勉強し続けることも、「1,000人に1人を見逃さない」という役割の上で、とても大切だと思っています。
例えば先日、「首が腫れていて不安だ」という患者さんが来ました。彼女は最初地域の内科クリニックへ行き「疲れているだけですよ」と言われ、不安だったので紹介状を書いてもらって大病院の内科にまで行ったそうなのですが、検査をされて異常がなかったので、「問題ない」と言われたそうです。それでも本人は不安だからと「もしかしたら女性系のホルモン不調なのかな」と思って、婦人科の私のところへやってきたんです。
私は問診(患者さんと話をして症状や経過を詳細に聞くこと)して、すぐに「とある疾患」を疑いました。そこで、それを説明して、信頼する大きな病院の先生へと紹介状を書きました。その後、そこの先生から患者さんに悪性リンパ腫が見つかったという返事をいただきました。私は婦人科ですが(笑)、ちゃんと内科の病気も見逃さなかったことで患者さんの笑顔につながったと、ほっとしました。。
ここ数年、他院からハシゴしてくる患者さんで、診断や投薬がちょっと違うな?というケースが多々みられます。もちろん、治療方法は多少何通りかあるので違うこともあるでしょう。また軽い不調なら大きな問題にはならないかもしれない。でも、大きな疾患はもし今回私が見過ごしてしまったら、もしかしたらその患者さんの命に関わるかもしれない。
地域の婦人科クリニックと言うと、重い病気の患者さんが来なくて、気楽なイメージを抱かれる人もいるでしょう。でも、そういった緊張感の中で治療をしているというのは、また大病院とは違っていて、少し意外に思われることなのかもしれません。
素人判断する前に、まずは信頼できる医師のところへ!
地域の婦人科医療を積み上げて10年以上が経過しますが、時代の変化について感じることはありますか?
大きな変化は、多くの人がインターネットで色々な情報を調べてから受診に来るようになったことですよね。特に婦人科領域は昨今“フェムテック”みたいな言葉もあって注目を集めるようになったこともあり、婦人科関連の情報に触れる機会も増えているではないでしょうか。
“フェムテック”は産業を中心に語られていることが多いですが、ビジネスが入り口であったとしても、病気の一歩手前を見つけるためには「予防医学」や「啓発活動」が大切だと思っているので、社会の注目が女性の健康やヘルスケアに向いてくれるのはいいことだと思います。
その反面、大きなデメリットもあります。インターネット上に医療関連の情報が溢れるようになったことで、自分で自分の症状をネット上の病名と照らし合わせて、最初から「この病気だ」って信じ込んで受診する人が増えてきていることです。特に、ネット上の医療っぽい情報が増えれば増えるほど、患者さんはわかっているようで訳がわからなくなってきていて、ますますこの傾向が加速しているなと感じます。
さっきお話ししたように、医者だって知識と経験を積み重ねないと、見逃してしまったり、間違った判断をしてしまうこともあるくらい、病気の診断は難しいんです。いい医者になるには教科書に書いてあることを丸暗記すればいい訳じゃなくて、勉強と経験の両方が要る。それを専門医でない人が素人判断するのはとても危険だということを覚えておいてください。
それでも、受診に来ている患者さんはまだいいんです。間違った自己診断を訂正して説得するのは大変だけれど、最終的には正しい医療を提供することができる。でも、自己診断で「病院に行かなくていい」と放置してしまった人を、私たちは救うことができません。私たちプロフェッショナルがきちんと診断しますから、体調に不安を感じたら、迷うことなく受診するようにしてください。

信頼できる婦人科を見つける3つのポイント
クリニックで受診しても、診察の話を聞くと不安になってしまいます。宗田先生は、信頼できるクリニックや婦人科の先生はどう選べば良いと思いますか?
前提として、もちろんドクターにも医療機関にも“完璧”はありません。完璧を目指して日々研鑽を積んではいますが、医療も人の成長にもゴールは無いですよね。最初に相談する婦人科の場合は、分娩・生殖・がんなど特定の分野にだけ特化した医師ではなく、幅広く診察し、必要な医療を見極められる医師が求められるのだと思います。その前提の上で、あくまで傾向としてですが、私だったら以下のポイントで選ぶことをお勧めします。
1つ目は、産婦人科専門医であることです。医師の資格には国家資格である医師免許の他に、学会が指定する条件をクリアすることで取得できる「専門医」という制度があるんですが、どんなに「婦人科」を名乗ったり、クリニックの診療科に「婦人科」を掲げていても、資格を持っていないということは、“学会が専門医に必要だと定める勉強や経験が足りていない”ということを意味します。
2つ目は、産婦人科領域で10年以上の経験を積んでいることです。これは後進の育成もしてきた私の経験から来る肌感覚ですが、4-5年くらいの経験ではまだまだ腕が未熟だなと感じるドクターも数多くいます。やっぱり学会(勉強)と診療(経験)を少なくとも10年くらいは積み重ねて、やっと信頼に足る腕になるのではないかと思います。医学部に進学して医師免許を取得し、研修期間を終えるのは、飛び級が無い限り最も若くても26歳です。つまり、若くても30代後半以降、できれば40歳前後以上の医師の受診をお勧めします。
3つ目は、キャリアの中で多くの期間を「大学病院」や「総合病院」で積み重ねていることです。さっき役割の違いでお話ししたように、地域のクリニックと大病院では、来る患者さんのタイプが違っています。
確率論から言って、地域の小さなクリニックでは、癌や特殊な病気、重篤な患者さんはあまり来院されず、ほぼ健康か軽い病気ばかりです。一方で、大病院は産婦人科に含まれるあらゆる領域に対応する上に、クリニックから様々な診断の難しい症状の患者さんが治療を受けに集まってきます。必要に応じて院内の他の診療科と連携する場面もたくさんあります。だから、“特定の専門領域だけを突き詰めるドクター”は別として、幅広く婦人科という意味であれば、クリニックでの診療経験と大病院の診療経験は、その経験値の濃度が違っていると思うんです。
婦人科に限らず、クリニックのウェブサイトには医師の経歴が掲載されていることが多いですよね。細かくチェックする方は少ないかもしれませんが、参考にしてみてもいいかもしれません。とは言え、どんなに経歴が立派で、腕が確かな医者であっても、人としての相性もあります。そこは難しいところですね。
婦人科を受診されている患者さんにも、その一歩手前の方々にも、メッセージがあればお願いします。

恵比寿の街に臨むクリニックの待合室にて
最近は少しずつ知られるようになってきましたが、女性の体というのは1ヶ月という周期でも、一生の間でも、主に女性ホルモンに左右されながら様々な体調の変化があります。そしてそれは個人差がとても大きく、女性どうしでも画一的でない部分があったりもします。こういったことはまだまだ意外と知らない人も多いな、と感じます。
それぞれの人の体に訪れる変化は、その時を迎えてみないと感覚的にはわからないものですが、今は様々な機会に知識として学んでおくことができます。女性の体にどんな変化が訪れるのか、どのように自分の体調を見極めれば良いのかは、最低限知識として身につけておいても良いでしょう。
ただ、情報があふれている現代だからこそ、「何を信じるか」を見極めることが大切です。先ほどの「信頼できる婦人科クリニックや医師選び」でも、信頼できる“人”ではなく“医師”と言ってきました。
医療機関を受診するのも、インターネット上で情報収集するのも同じです。“医療っぽい”情報発信をする人たちやクチコミはたくさん存在します。時には体に関連するサービスを提供する医師以外お職業の方にヘルスケアに関するアドバイスをされて、戸惑うこともあると思います。これもやっぱりきちんと経験を積んだ医師、専門医が発信しているものかどうか、信じて良いものかどうか、見極めて欲しいと思います。
体に不安なところや不調があって困ったら、ぜひクリニックに相談に来てください。あなたのその不調がもし重篤な疾患に繋がるものだったら、早めに見つけておく必要があります。逆に深刻なものでないとわかったら、きっと安心できるはずです。
日本には、そんな患者さんのために日々研鑽を積み重ねている産婦人科医がたくさんいます。ぜひいい先生に巡りあって、健康な人生を送ってください。
女性からだ情報局編集部では、これまで数十人の産婦人科専門医へインタビューを行ってきた。産婦人科の道を選んだ理由も、産婦人科医療にかける想いも十人十色だったが、宗田医師への60分を超えるインタビューは、総じてこの先生が“他の医師から信頼されるのがよくわかるな”と感じさせるものだった。
宗田医師が語る「1,000人に1人を見逃さない」という心構え。それはわずか0.1%という確率に過ぎない。18年間で延べ13万5,000人の診察を積み上げたとするなら、その0.1%は135人。およそ2ヶ月に1人いるかいないか、という計算になる。それでも、その1人を見逃さないために、知識を仕入れ、技術を磨き、緊張感の中で診察にあたる。その姿は“プロフェッショナル”以外の何ものでもない。そしてそれは、時には命をも脅かす疾病に対する“医療”が、単に直接的な投薬や施術だけでなく、早期発見や適切な初動にもあることを改めて教えてくれる。
これまで積み上げた婦人科のノウハウを惜しげもなく後進に伝え、地域に還元し、そしてこれだけの実績がある今でも学び、活躍を続ける宗田医師。あなたがいつも診察室で会う婦人科医にも、こんな背景が隠されているかもしれない。ぜひそんな地域の医師に巡り会っていただきたい。