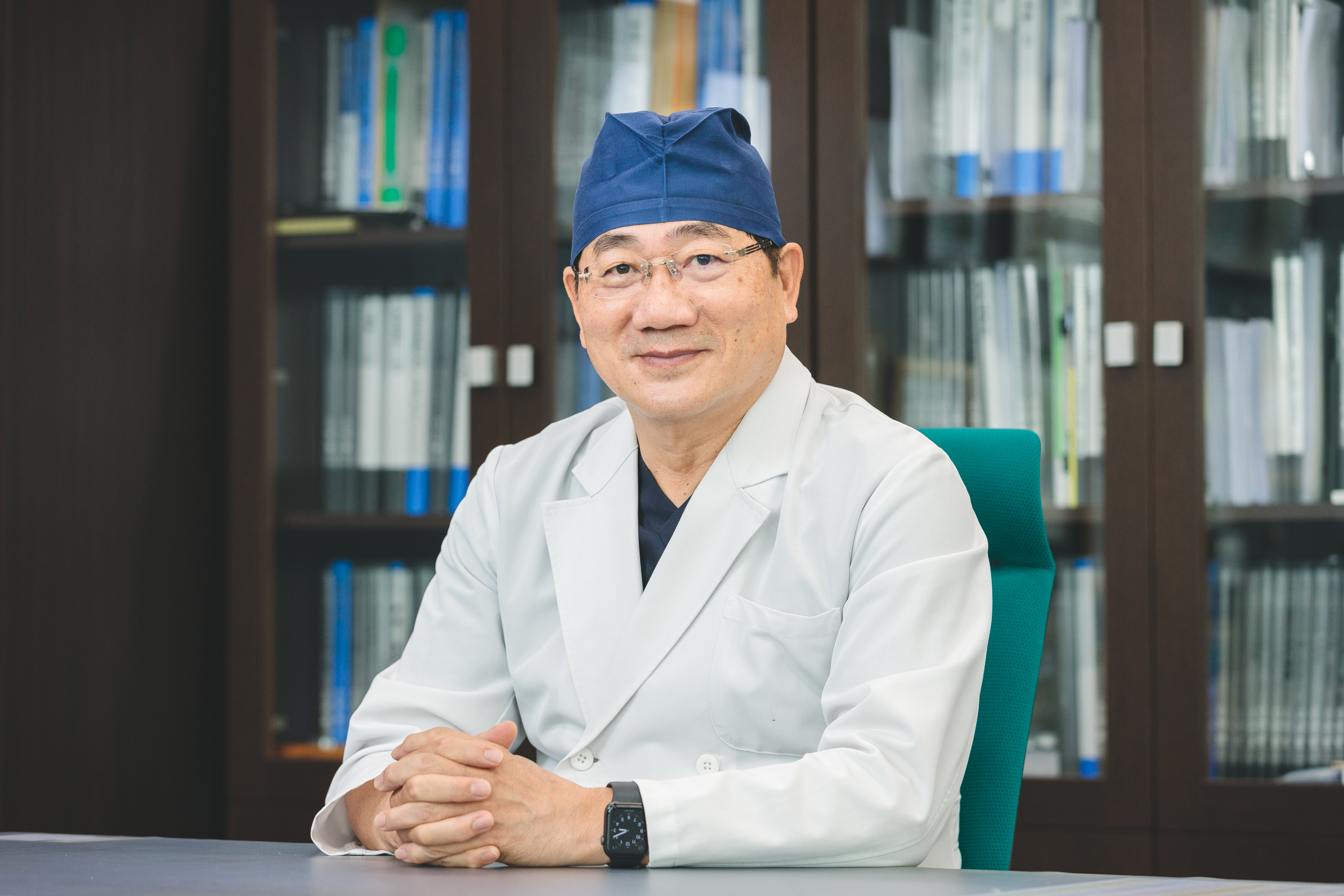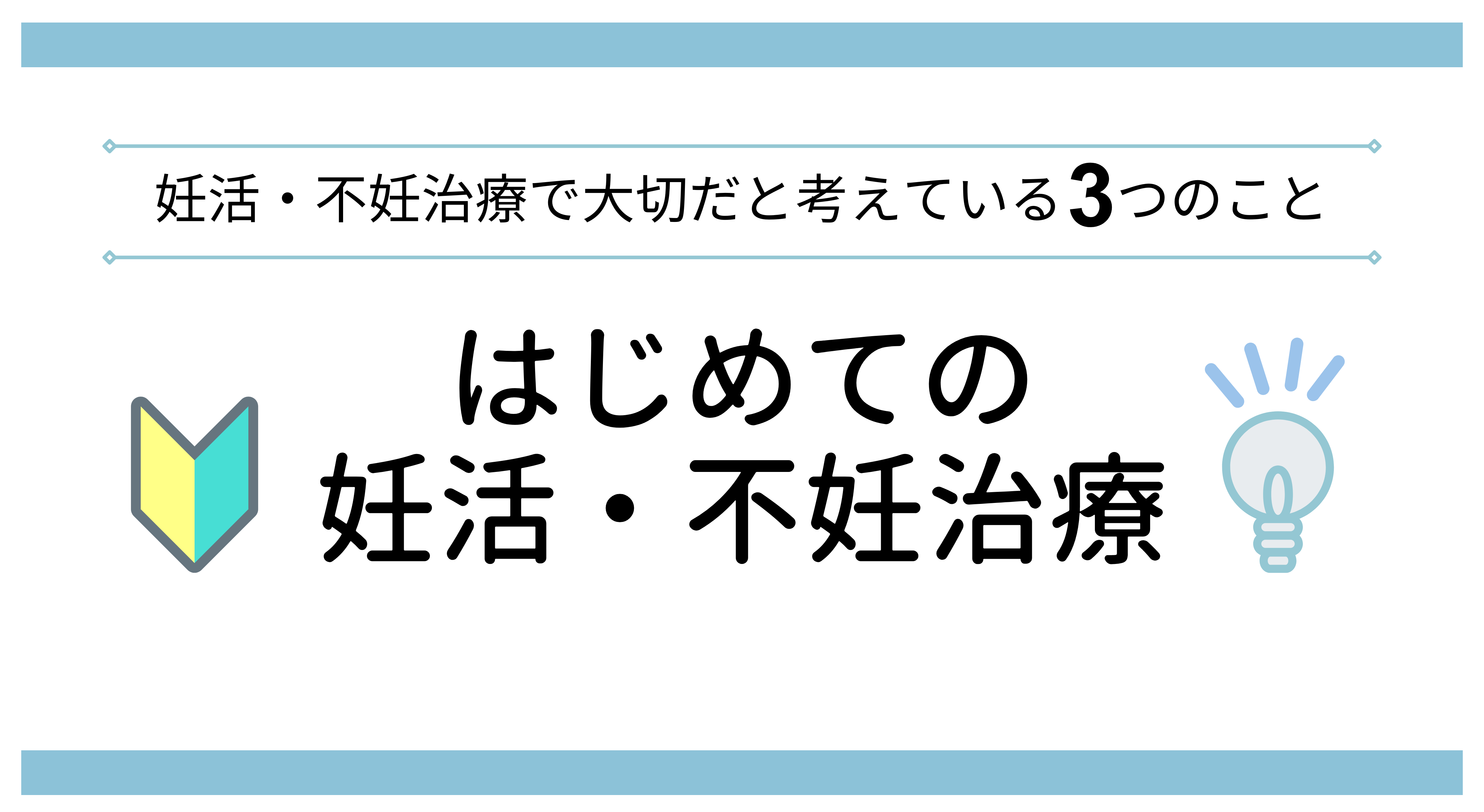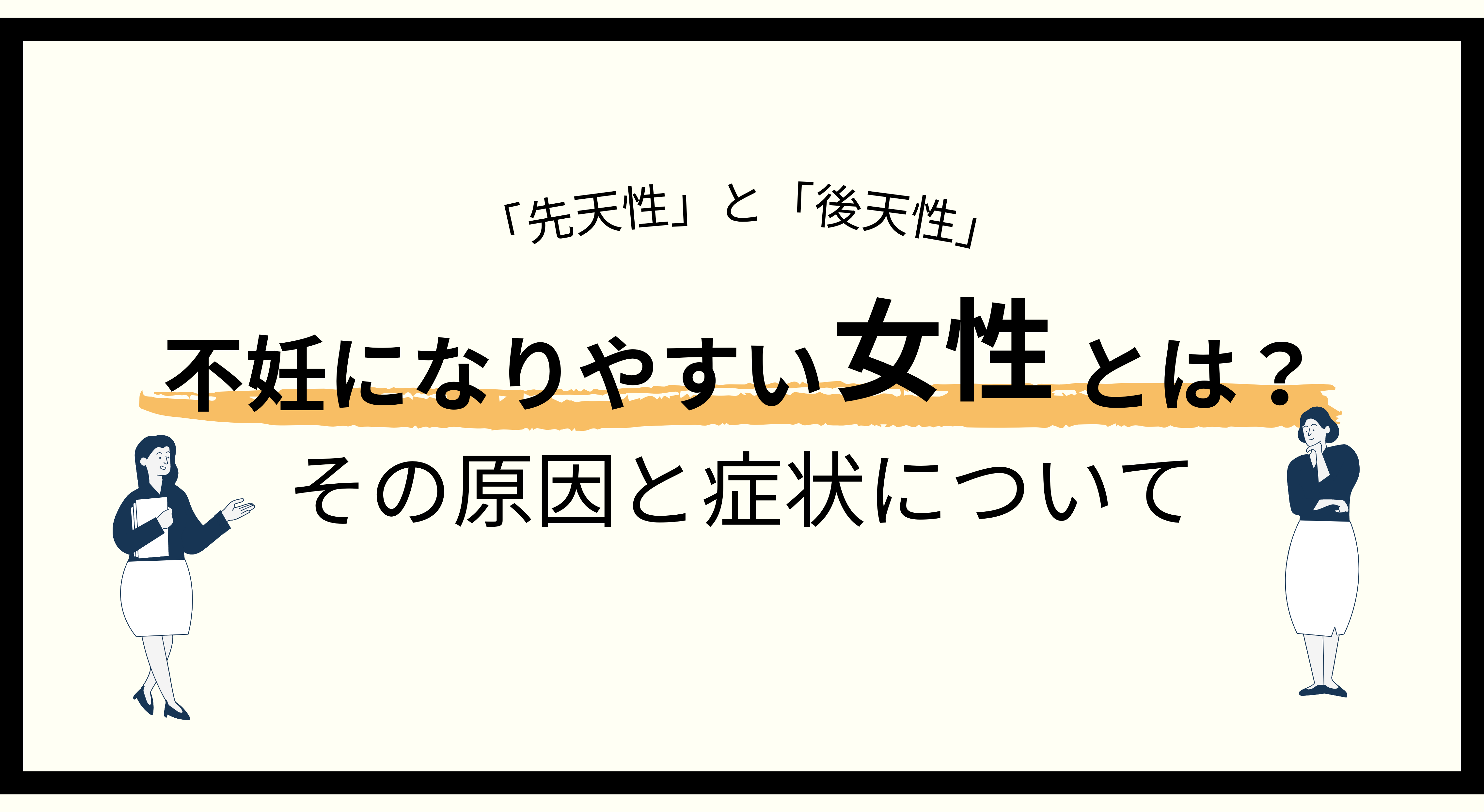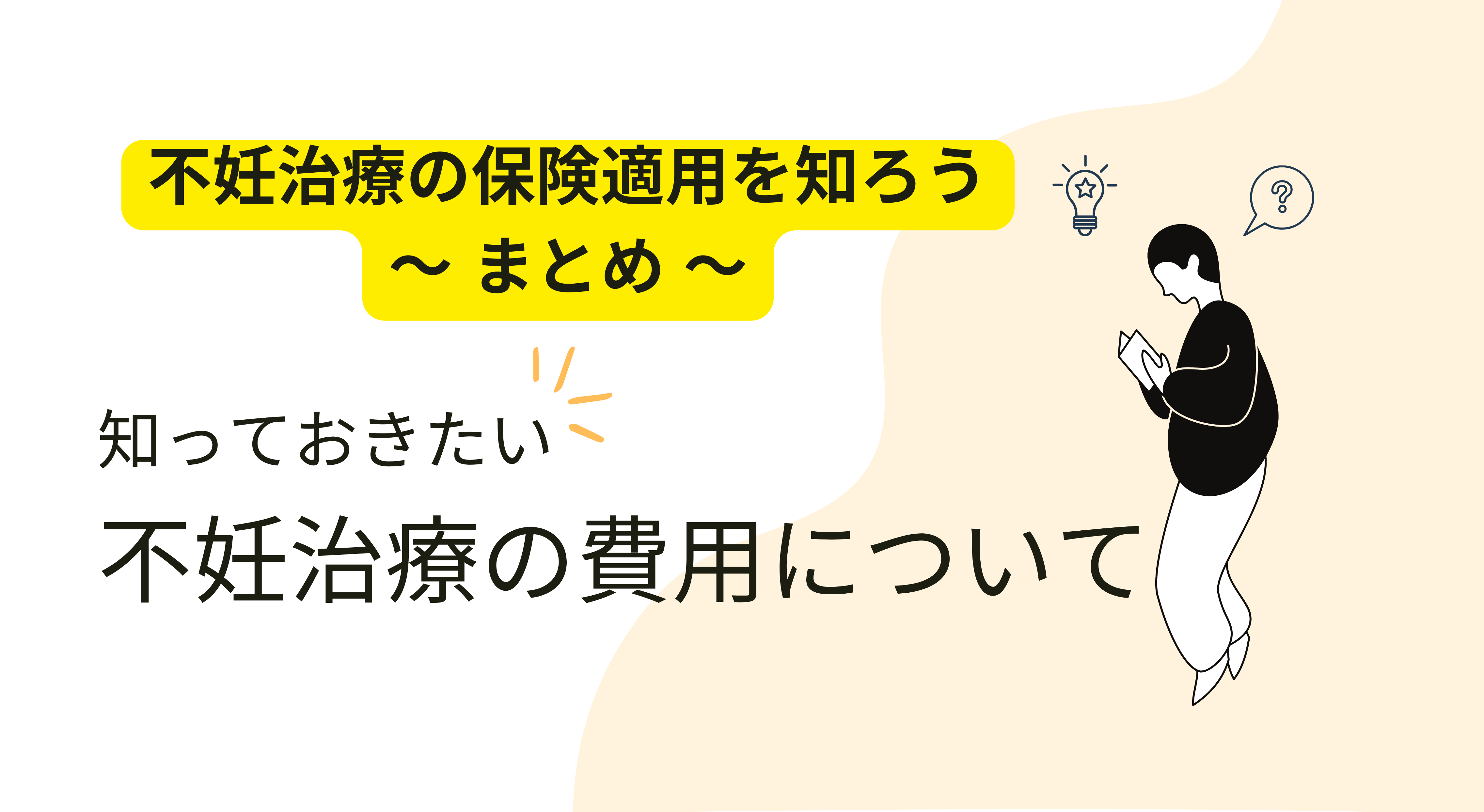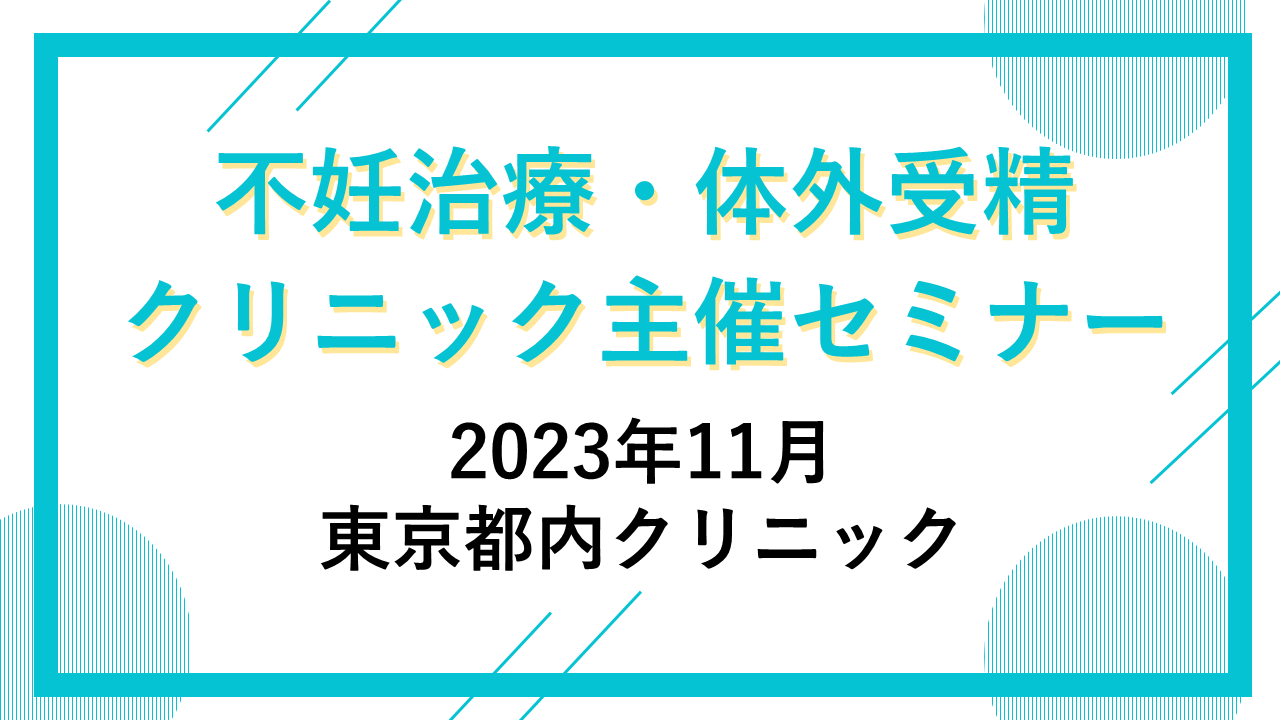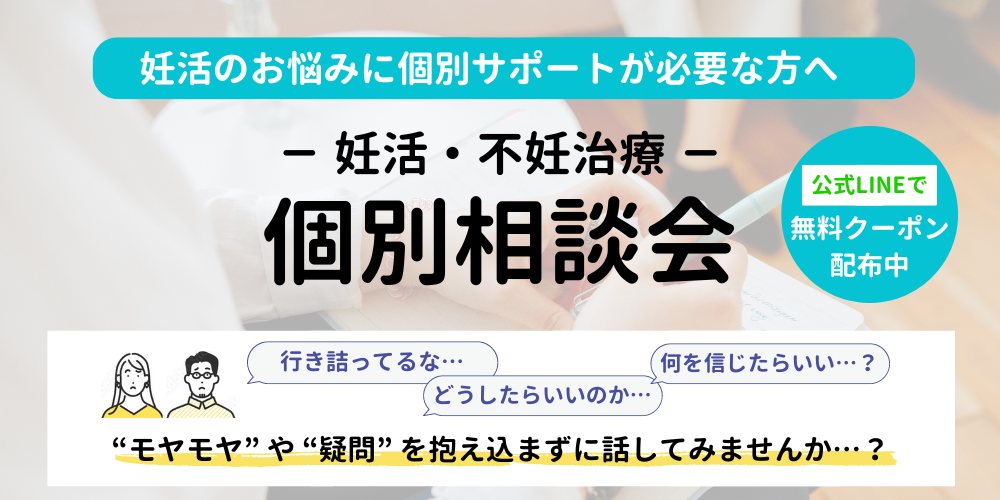日本国内の体外受精件数を地域別に見たとき、東京都・大阪府に次いで3番目の多さなのが愛知県だ。人口の面で言えば当然の話のようでもあるが、愛知県の中心地である名古屋、その駅の目の前には、この地域の不妊治療をリードしてきたクリニックがある。浅田義正(あさだ よしまさ)理事長率いる「浅田レディースクリニック」だ。
この浅田先生も、草創期から日本の生殖医療の発展をリードしてきた1人だ。女性からだ情報局の体験記でも取り上げているが、東京やその他の地域に在住していてさえ、治療のために名古屋まで遠距離を通い、お子さんを授かった人が多数存在する。お子さんを願う気持ちが距離を超え、浅田レディースクリニックが、その想いに応えてきた。
そんな浅田レディースグループが2018年、3つめとなるクリニックを東京に開院した。品川駅の港南口を出ると、目の前に飛び込んでくる巨大な看板を目印に、3分ほどまっすぐ進むと現れるオフィスビルの中に「浅田レディース品川クリニック」はある。
オフィスビルの中にあるので、入り口も企業オフィスに入るのと同じエレベーターだ。不妊治療のクリニックには、このスタイルのところが数多くある。仕事の合間に治療に訪れることができるほか、「不妊治療に通っている」ことを悟られにくい側面もある。
このオフィスビルの1フロアまるごとかけて実現されているのが、長年不妊治療をリードしてきた浅田医師のノウハウがすべて詰まった最新クリニックだ。診察室や相談室のみならず、受付や待合室、動線、培養室、裏側のスタッフルームや応接室に至るまで、浅田医師のきめ細やかな意識が行き届いていることがわかる。
特徴的なのは、単に診察だけでなく、ご自身で培養プロセスまで行うからこそ実現した、企業との共同開発や特注のシステムを導入したクリーンルーム(胚培養室)。そして、いつ、どこで、どのスタッフが担当しても全く同じ高い医療水準が実現できるようシステマチックに徹底管理された運用面だ。
今や3院あわせて累計2万5,000名以上の「体外受精による妊娠」を実現させてきた浅田レディースグループ。理事長である浅田医師は、毎週名古屋と東京を行き来しながら、その合間に学会などに顔を出すという多忙な日々を送っている。そしてなお、常に医療技術の研鑽や臨床現場の改善を怠らないのだ。
そのエネルギッシュな毎日の裏には、どんな思いがあるのか。インタビューで尋ねてみた。(全2回の前編)
オイルショックが変えた工作少年の運命
浅田先生は最初、工学系へと進学されていたとか。どんな経緯で医師になられたのでしょうか。
私は医者の家系ではないので、最初から医師を目指していた訳ではないんですよ。工作が大好きな少年だったし、進路は迷いなく工学部を志望していました。最初の大学受験では東大・京大の工学部を受験したのですが落ちてしまい、一浪して早稲田と慶応の理工学部に合格。進学先は早稲田を選びました。
進学してみてわかったのですが、当時はオイルショックから間もない頃。早稲田を卒業してさえも就職が厳しいという噂が流れていました。工学部だったのでなおさらそうだったのかもしれません。
私の下宿先には、医学部受験に失敗して三浪したのちに早稲田の理工学部に入学した同級生がいました。その彼がいつも「医者は景気に左右されないから最高なのになぁ」とばかり言っていたんです。毎日のようにその言葉を聞かされて、私はどんどん感化されてしまって。
実は高校のころ同級生には医者の息子が多くて、「医学部へ行けないから工学部を目指すんだろう」とからかわれるたびに、腹立たしいなとも思っていたんです。
結局、同じ下宿の私を含めた3人が、医学部へ入学し直すことになりました。私は名古屋大学の医学部へ進み、1982年に卒業しています。
まさに運命を変えた下宿先ですね。数ある診療科の中から産婦人科を選ばれたのはなぜでしょう?
そんな経緯で選んだ医者の道ですから、どの科に進むかのこだわりは最初は特にありませんでした。
すべての科をめぐる大学でのローテート研修が終わり、まずは救急医療を身につけるために救急救命センターのある病院に行きました。その後は内科の様々な分野を回っていたんです。
内科にいた私が方向を変え、産婦人科を目指すきっかけとなった出来事は今でもはっきりと覚えています。珍しいかもしれませんが、私が産婦人科に進もうと決意したのは、研修で訪れた産婦人科ではなく、1人の医師として内科にいたときでした。そこで出会った1人の患者に、医療に向き合う覚悟を問われたような気がします。
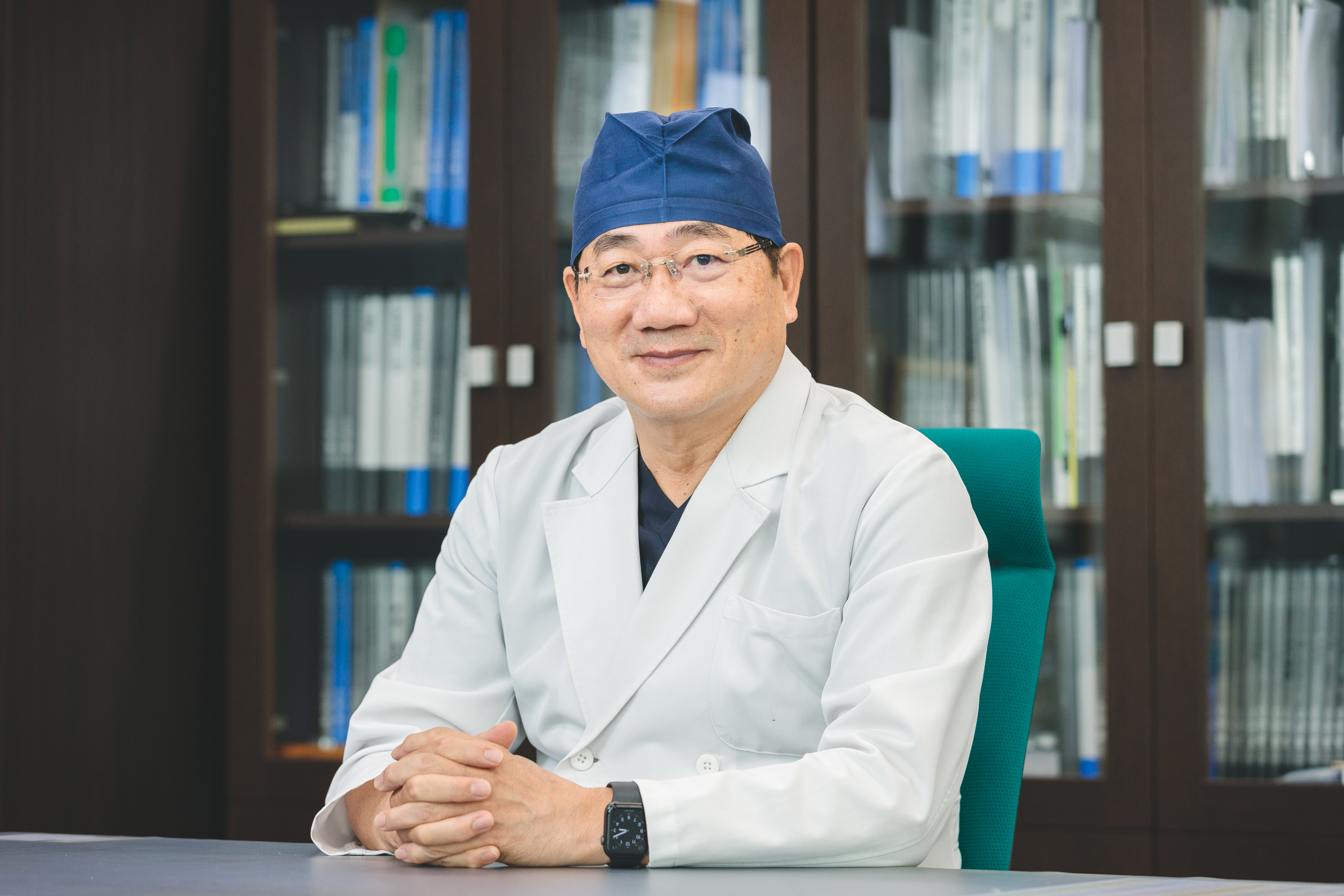
命を懸けて教えてくれた16歳の白血病の少女
当時、私は白血病を患う16歳の少女の主治医となりました。“最後の主治医”です。
1980年代、まだまだ白血病は不治の病とされていた時代。白血病はがんの一種ですが、患者に対してがんを告知することも当時はあまりありませんでした。
彼女には、2日に1回輸血を行っていました。ドナーから血小板を採取し、輸血をする。今では輸血の環境もずいぶん整ってきましたが、当時はとても大変で、日々繰り返される輸血に私は疲れきってしまっていました。
間もなく彼女は息を引き取りました。16歳で白血病で亡くなるなんて、社会全体から見るととても低い確率ですが、病院では日々こういった患者さんが闘っています。元気になって社会に復帰される方もいれば、どんなに医学が進歩しても、残念な結果が待ち受けている場合もあります。
彼女が亡くなったとき、私が最初に感じたのは、悲しみでも悔しさでも無力感でもなく、ただひとつ「仕事が終わった」という安堵感でした。
もちろん前任の主治医たちも含めて、彼女には当時我々ができる最高の医療を施したことでしょう。私は新米内科医に過ぎなかったし、ハードな毎日に疲れ果ててもいました。40年前はどんな職場も今よりずっとハードワークでしたから。
それでも、人が亡くなったことに、ましてや16歳の若者が亡くなったことに対して「仕事が終わった」と感じてしまった自分を許すことができなかった。その想いは日に日に大きくなりました。
同じ医療をやるのなら、自分が施す医療を、1つでも多くの命につなげていきたい。罪滅ぼしではありませんが、この経験を経て、より命の誕生に近い産婦人科を志すようになりました。
産婦人科・生殖医療に携わるようになって40年以上経ちます。ありがたいことに、これまで数えきれないほどの命の誕生に関わってきました。自らの命を懸けて私に教えてくれた、あの16歳の白血病の少女がいたからこそ、今の私があるのだと思っています。
浅田先生がこれだけ精力的に取り組み、実績を残されてきた背景にはそんなストーリーがあったんですね。産婦人科の中で生殖医療に進まれたのはなぜですか?
2年半をかけたローテート研修と内科での勤務、そして産婦人科への異動を経て、その後は大学の医学部へと戻ることになりました。
最初の配属先が周産期(※編集部注:出産関連の領域のこと)だったのでお産の研究をしようとしていましたが、1年くらい経ったころ、生殖医療の人手が足りないので、そちらの研究室に移るように命じられました。だから、最初は自分で選んだというより大学内での人事の辞令ですね。

浅田レディースグループの1つ、浅田レディース勝川クリニック
「顕微授精」が工作少年のライフワークに
私はもともと内科にいたこともあって、大学に戻ったときから更年期外来を担当していました。更年期の治療はホルモン補充療法のような投薬をすることが多いので、産婦人科の中でも「内科っぽい」領域なんです。
ただ、この更年期医療も生殖医療も、当時は国内ではまだほとんど歴史がなく、教わる人もいないために、すべて自分で勉強していかなくてはいけないような状況でした。教わる師匠がいないというのは、勉強そのものが大変である反面、どんどん自分で進めていくこともできます。そんな風に色々と勉強していくうちに、「生殖医療って面白いな」と思い始めていました。
大学では5年ほど非常勤医員をやりましたが、一度きちんと研究がしてみたいと思い、アメリカへ留学することにしました。生殖医療に惹かれていた私は、最初は「卵子の研究がしたい」と伝えていたものの、当時まだ珍しかった顕微授精との出会いがあり、結局これがライフワークとなっています。
先ほどお話ししたように、私はもともと工学部に進学していたような理工学系の人間ですから、技術が重要な顕微授精とはとても相性が良かった。そもそも興味深いなと思えたし、必要となる考え方も身についていました。何より昔から手先が器用な工作少年あがりだったので、英語が話せなくても不器用なアメリカ人の中でチームの一員となれたのもの幸運だったと思います。
一度は工学部に進学したかつての工作少年が、様々な出会いを経て医学部・内科・産婦人科・そしてついにアメリカでの顕微授精の道へ。
では、研究者として大学に所属していた浅田医師は、どのようにして現在に続く「浅田レディースクリニック」グループを立ち上げるに至ったのか。その後の経緯に迫ります。(後編を読む)